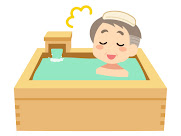卵にはコレステロールが多く含まれているため、かつては「血中コレステロール値が高くなるから卵の食べ過ぎは控えた方がいい」などと言われることがありましたが、後の調査で食べ物から得られるコレステロールが血中コレステロール値の上昇に関わっているという証拠はないことがわかっています。新しい研究で、高齢者が卵を食べることが心臓の健康状態を良くし、早死にのリスクさえも減らす可能性があることがわかりました。
参加者はゆで卵、ポーチドエッグ、目玉焼き等の卵料理について「全く食べない/ほとんど食べない」「月1~2回」「週1~2回」「週3~6回」「毎日」「1日に数回」の選択肢から回答を選びました。なお、アンケートでは卵の種類については問われていませんでしたが、ワイルド氏は「オーストラリアの卵の消費量はほとんどが鶏卵である」と補足しています。
ワイルド氏らが参加者のうち特定の因子を持つ人を除いた8756人をピックアップし、健康状態との関連性を調べたところ、週に1〜6回卵を食べる人は、ほとんど食べない人や全く食べない人に比べて、研究期間中の死亡リスクが最も低かったことがわかりました。具体的には心血管疾患を原因とする死亡が29%、全死亡で17%低いという結果でした。ただし、心血管疾患および全死亡リスクは、「卵を毎日食べている人」と「ほとんど食べない人や全く食べない人」の間に差は認められなかったとのことです。加えて、がん死亡率と卵の摂取量の間に関連は認められませんでした。
全体としては、8756人のうち2.6%が毎日卵を食べ、73.2%が毎週卵を食べ、24.2%が卵をほとんど食べないか全く食べませんでした。加えて、卵をほとんど食べないか全く食べまない人と、毎週または毎日食べる人を比較すると、前者のグループは年齢が高く、正式な教育歴が12年未満であり、身体活動レベルが低く、非飲酒者であり、食事の質が低い傾向があったとのこと。なお、食事の質が中程度~高程度の人に絞って分析したところ、卵を週に1〜6回食べている人は卵をほとんど/全く食べない人に比べて心血管疾患の死亡リスクがさらに低かったとのことです。
ワイルド氏らは「高齢者が週に1~6回卵を食べることは、全死亡リスクと心血管疾患の死亡リスクの低さと関連していることがわかりました。オーストラリアの食事ガイドラインでは、成人に週7個までの卵を食べるよう推奨していますが、私たちの調査結果に基づくと、高齢者に対する指針を調整する余地があると考えられます」と述べました。